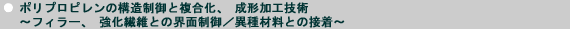 |
 |
 |
ポリプロピレンの精密合成 |
|
 |
| 1節 | ポリプロピレンの精密合成 |
| 1. | プロピレンの立体特異的重合 |
| 1.1 | 立体規則性の定義 |
| 1.2 | 末端規制と触媒規制 |
| 1.3 | Ziegler-Natta 触媒によるプロピレンの iso-特異的重合 |
| | −Ziegler-Natta 触媒における重合活性種モデル |
| | −Lewis 塩基の添加による立体特異性の制御 |
| 1.4 | 均一系触媒によるプロピレンの立体特異的重合 |
| | −メタロセン触媒によるiso-特異的重合 |
| | −タロセン触媒によるsyn-特異的重合 |
| | −タロセン以外の触媒を用いた立体特異的重合 |
|
|
| 2. | リビング重合 |
| 2節 | ポリプロピレンの立体選択的重合に向けた触媒技術 |
| 1. | プロピレンのイソ特異的重合反応 |
| 1.1 | プロピレンの立体規則性 |
| 1.2 | 立体規則性の発現機構 |
| 1.3 | メタロセン触媒によるプロピレンのイソ特異的重合 |
| 1.4 | ポストメタロセン触媒によるプロピレンのイソ特異的重合 |
| 3節 | プロピレン重合用触媒の選び方,使い方 |
| 1. | プロピレン重合用触媒の歴史 |
| 2. | ポリプロピレンと触媒の選択 |
| 3. | THC触媒(Mg担持系固体触媒成分) |
| 4. | U-ドナー |
|
| |
 |
ポリプロピレンの構造制御,改質技術 |
|
 |
| 1節 | ポリプロピレンのせん断流動中結晶成長 ~そのメカニズムと観察~ |
| 1. | 試料および実験 |
| 1.1 | 試料 |
| 1.2 | 実験装置 |
| 1.3 | 温度条件,せん断条件 |
| 2. | 結果と考察 |
| 2.1 | HSPOM 測定 |
| 2.2 | 小角X線散乱・広角X線散乱 |
| | −小角X線散乱の結果と配向構造の相関 |
| | −広角X線散乱の結果 |
| 2.3 | 結晶化度の減少についての議論 |
| 2節 | 成形プロセス中のポリプロピレンの配向結晶化機構と高次構造制御 |
| 1. | PP溶融紡糸における結晶化挙動の吐出温度、紡糸速度依存性 |
| 2. | 低立体規則性PPの高速溶融紡糸 |
| 3. | 複合紡糸による応力制御の効果 |
| 4. | 溶融紡糸過程の高次構造形成過程のオンライン計測 |
| 3節 | ブロックポリプロピレンの構造解析と材料特性の予測 |
| 1. | 材料構造の分析 |
| 1.1 | 13C-NMR による共重合組成分析 |
| 1.2 | 高温 GPC による分子量分布測定) |
| 1.3 | パルス NMR によるマクロな組成分析 |
| 1.4 | FT-IR による結晶性評価 |
| 2. | 材料構造と物性の関係 |
| 2.1 | 一次の相関分析による概要把握 |
| 2.2 | 連鎖分布と材料特性の関係 |
| | −連鎖構造と材料強度との関係 |
| | −連鎖構造と剛性の関係 |
| | −連鎖構造と耐衝撃性の関係 |
| 2.4 | パルス NMR によるマクロな組成と材料物性の関係 |
| | −マクロな組成と材料強度の関係 |
| | −マクロな組成と剛性との関係 |
| | −マクロな組成と耐衝撃性の関係 |
| | −マクロな組成と流動性の関係 |
| 2.5 | 材料物性の予測 |
| 4節 | ポリプロピレンの分子配向制御による衝撃強度向上,破壊形状制御 |
| 1. | 結晶核剤による分子配向の制御 |
| 1.1 | 結晶核剤 |
| 1.2 | 樹脂中での NU-100 の溶解・析出挙動 |
| 2. | シート成形体 |
| 2.1 | シート成形体の分子配向 |
| 2.2 | シート成形体の動力学的性質 |
| 2.3 | シート成形体の力学的性質 |
| 3. | 射出成形体 |
| 3.1 | 射出成形体の配向制御 |
| 3.2 | 射出成形体の機械特性 |
| 5節 | ポリプロピレンの剛性・耐衝撃性向上と用途展開 |
| 1. | ポリプロピレンの剛性の向上 |
| 1.1 | 立体規則性の制御 |
| 1.2 | 分子量分布の制御 |
| 2. | ポリプロピレンの耐衝撃性の向上 |
| 2.1 | モルフォロジーの効果 |
| 2.2 | バイポリマー相の組成 |
| 3. | 透明・耐衝撃インパクトコポリマーの新しいカテゴリー |
| 6節 | ポリプロピレン/ CO2 由来ポリカーボネートのブレンドと耐衝撃性向上 |
| 1. | ポリプロピレン/ CO2 由来ポリカーボネートのブレンド |
| 1.1 | 基本物性 |
| 1.2 | 力学特性と変形機構 |
| 1.3 | 破壊機構 |
| 2. | ポリプロピレン/イオン液体をドープしたCO2由来ポリカーボネートとのブレンド |
| 2.1 | 基本物性 |
| 2.2 | 力学特性 |
| 2.3 | 破損機構 |
| 7節 | ポリプロピレンへの難燃剤配合とそのブリードアウト対策 |
| 1. | PPの難燃化の方法 |
| 1.1 | 臭素系難燃剤によるPPの難燃化 |
| 1.2 | 金属水和物系難燃剤によるPPの難燃化 |
| 1.3 | リン酸塩系難燃剤によるPPの難燃化 |
| 2. | ブリードアウト |
|
|
| 2.1 | ブリードアウトとは |
| 2.2 | ブリードアウトの影響 |
| 2.3 | ブリードアウト対策 |
| | −ブリードアウト対策の分類 |
| | −ノンハロ難燃剤のブリードアウト主原因 |
| | −ノンハロ難燃剤のブリードアウト対策法 |
| 2.4 | APPのブリード現象と対策事例 |
| | −ブリードアウト現象 |
| | −ブリードアウトの対策 |
| 3. | ノンハロリン酸塩系難燃PPの開発事例 |
| 3.1 | リン酸塩系難燃PPの技術 |
| 3.2 | リン酸塩系難燃PPの特徴 |
| 8節 | ポリプロピレン樹脂用高分子型帯電防止剤の機能と効果 |
| 1. | 帯電防止剤の役割 |
| 2. | 高分子型帯電防止剤(永久帯電防止剤) |
| 3. | ポリプロピレン樹脂用高分子型帯電防止剤 |
| 9節 | 黒鉛粉添加によるポリプロピレンの導電化及び高熱伝導化技術 |
| 1. | プラスチックの導電化及び高熱伝導化技術の現状 |
| 2. | 黒鉛粉の物性とその特徴 |
| 3. | 黒鉛粉を利用した導電化 |
| 4. | 黒鉛粉を利用した高熱伝導化 |
| 5. | 黒鉛粉によるプラスチックの導電化及び高熱伝導化技術の今後の展望 |
| 10節 | パーフルオロアルキル化合物によるポリプロピレン表面への撥水撥油性付与 |
| 1. | 表面張力と撥液性の関係 |
| 1.1 | 表面張力 |
| 1.2 | ヤングの式 |
| 1.3 | 樹脂表面の表面エネルギー |
| 2. | パーフルオロアルキル化合物の特徴 |
| 2.1 | パーフルオロアルキル基 |
| 2.2 | パーフルオロアルキル化合物の構造 |
| 2.3 | パーフルオロアルキル化合物の撥水撥油性 |
| 3. | ポリプロピレンへのパーフルオロアルキル化合物による撥水性撥油性の付与 |
| 3.1 | 表面処理 |
| 3.2 | 内添処理 |
| 11節 | シリコーン系添加剤の配合によるポリプロピレンへの耐擦傷性付与 |
| 1. | シリコーン系添加剤の熱可塑性樹脂への使用 |
| 2. | シリコーン含有マスターペレットによる耐擦傷性改良 |
| 3. | ポリマー中でのシリコーンアンカー:乾式シリカの役割 |
| 4. | シリコーン系添加剤の耐擦傷性付与効果 |
| 12節 | アロイ・ブレンド・複合化によるポリプロピレンのトライボロジー特性制御 |
| 1. | プラスチックのトライボロジー特性 |
| 1.1 | プラスチックの摩擦特性 |
| 1.2 | プラスチックの摩耗特性 |
| 1.3 | プラスチックのトライボロジー特性に及ぼす諸因子 |
| 2. | プラスチックのトライボロジー特性の制御法 |
| 3. | ポリマーアロイ・ブレンド化によるPPのトライボロジー特性の制御 |
| 3.1 | ポリマーアロイ・ブレンド化によるプラスチック系トライボマテリアルの材料設計ポイント |
| 3.2 | ポリマーアロイ・ブレンド化によるPPのトライボロジー特性の制御例 |
| 4. | 複合化による PP のトライボロジー特性の制御 |
| 4.1 | 複合化によるプラスチック系トライボマテリアルの材料設計ポイント |
| 4.2 | 多成分系複合化によるプラスチックのトライボロジー制御について |
| 4.3 | 複合化によるPPのトライボロジー特性の制御例 |
| 13節 | ポリプロピレンフィルム中に含まれる添加剤のブリードメカニズム |
| 1.2 | 段階移行モデル |
| 2. | 添加剤のブリード実験 |
| 2.1 | 試料 |
| 2.2 | サンプル調製とブリード成分の定量 |
| 3.2 | 段階移行モデルを用いたブリード解析 |
| 3.1 | スリップ剤のブリード解析 |
| 3.2 | UV 吸収剤のブリード解析 |
| | −MDを用いた飽和溶解度の評価 |
| | −MDを用いた拡散係数の評価 |
|
| |
 |
ポリプロピレンの劣化対策,耐久性向上 |
|
 |
| 1節 | ポリプロピレンの劣化要因とその対策 |
| 1. | 劣化の化学的な側面:耐熱老化性を事例として |
| 1.1 | 固体の化学反応 |
| 1.2 | 耐熱老化現象 |
| 1.3 | 添加剤と顔料の影響 |
| 1.4 | 成形による高次構造と劣化 |
| 1.5 | 溶融体の熱劣化 |
| 2. | 劣化の機械的な側面:ヒンジ特性を事例として |
| 2.1 | 機械的な強度の劣化 |
| 2.2 | ヒンジ特性 |
| 3. | その他の劣化について |
| 4. | 劣化の対策 |
| 4.1 | 成形品の表面の劣化,外観の長期的な悪化の対策 |
| 4.2 | 成形品の全体の劣化,物性の長期的な悪化の対策 |
| 2節 | ポリプロピレンの加工,使用における劣化と添加剤選定のポイント |
| 1. | PPの劣化と安定剤 |
| 1.1 | 劣化機構 |
| 1.2 | 添加剤と安定剤 |
| 2. | 酸化防止剤の働きと種類 |
| 2.1 | フェノール系酸化防止剤 |
| 2.2 | リン系酸化防止剤 |
| 2.3 | イオウ系酸化防止剤 |
| 2.4 | 金属不活性化剤 |
| 3. | 光安定化の働きと種類 |
| 3.1 | 紫外線吸収剤 |
| 3.2 | 光安定剤 |
| 4. | 安定剤の実践的用法 |
| 4.1 | 成形加工時の安定化と注意点 |
| 4.2 | 加温使用製品での安定化処方と注意点 |
| 4.3 | 屋外使用製品での安定化処方と注意点 |
|
|
| 3節 | ポリプロピレンシート中の光安定剤分析 |
| 1. | 反応熱脱着GC測定 |
| 1.1 | システムの構成と測定手順 |
| 1.2 | PP中の高分子量HALSの高感度直接分析 |
| 1.3 | 紫外線照射に伴うPP中のHALSの化学構造変化 |
| 2. | 固体試料調製法によるMALDI-MS測定 |
| 2.1 | 固体試料調製MALDI-MSの測定手順 |
| 2.2 | PP 中の高分子量HALSの直接分析 |
| 2.3 | PP シート中HALSの安定化挙動の解析 |
| 4節 | 微量ポリプロピレンの添加剤分析技術 |
| 1. | ピンポイント濃縮法とは |
| 2. | 微小PP片における添加剤分析の事例 |
| 3. | ミクロGPC分取による高分子量添加剤の分析 |
| 3.1 | ミクロGPC分取システムの特長 |
| 3.2 | ミクロGPC分取の適用例 |
| 5節 | ケミルミネッセンス(微弱発光)法によるポリオレフィンの酸化劣化評価 |
| 1. | ケミルミネッセンス(CL:chemiluminescence)法とは |
| 2. | 酸化劣化とCL |
| 3. | CL測定方法 |
| 4. | 測定例 |
| 4.1 | ポリプロピレンの劣化とケミルミネッセンス |
| | −劣化材料の作製 |
| | −劣化材料の評価(ペレット形状) |
| | −酸化防止剤添加 PP のケミルミネッセンス |
| | −化学的評価法との比較 |
| | −物理的評価法との比較 |
| 4.2 | ポリアミドの劣化とケミルミネッセンス |
| 5. | 発光画像測定例 |
| 5.1 | 酸化 PP の発光画像 |
| 5.2 | 酸化 PA の発光画像 |
|
| |
 |
ポリプロピレン/フィラー,強化繊維の複合化と機械的特性向上 |
|
 |
| 1節 | PP ブレンド,複合材料の機械的特性に影響を及ぼす因子 |
| 1. | 弾性率 |
| 2. | 衝撃強度 |
| 2.1 | エラストマーによる衝撃強度の変化 |
| 2.2 | フィラーによる衝撃強度の変化 |
| 3. | 引張降伏応力 |
| 3.1 | 分散粒子による引張降伏応力の変化 |
| 3.2 | 粒子径による引張降伏応力の変化 |
| 3.3 | PP/フィラー界面接着による引張降伏応力の変化 |
| 2節 | ポリプロピレン/強化繊維の複合化における相溶性の改善技術 |
| 1. | 接着のメカニズム |
| 2. | 相溶化剤の役割 |
| 3. | 相溶化剤の種類 |
| 3.1 | 極性モノマー共重合体 |
| 3.2 | グラフト変性ポリマー |
| 4. | グラフト反応のメカニズム |
| 4.1 | 無水マレイン酸変性ポリエチレン |
| 4.2 | 無水マレイン酸変性ポリプロピレン |
| | −グラフト構造 |
| | −グラフト率 / 分子量バランス |
| 5. | 相溶化剤の効果 |
| 5.1 | ガラス繊維強化ポリプロピレン(GFRPP) |
| 5.2 | ウッドプラスチック |
| 5.3 | フィラー分散 |
| | −水酸化マグネシウム |
| | −有機化モンモリロナイト |
| 3節 | リアクターグラニュール技術によるポリプロピレンナノコンポジットの調製とその特性 |
| 1. | PP/TiO2 ナノコンポジット |
| 2. | PP/Al2O3 ナノコンポジット |
| 3. | PP/Mg(OH)2 ナノコンポジット |
| 4節 | シリカ/ポリプロピレン系ナノコンポジットの結晶化とその制御因子 |
| 1. | 結晶核の形成・結晶成長の基礎 |
| 1.1 | 古典的核形成理論 |
| 1.2 | 高分子の結晶化機構 |
| 2. | 分散ナノシリカとiPP母相界面のぬれ性が異なるナノコンポジットにおけるiPP母相の結晶化挙動 |
| 2.1 | 対象としたシリカ/iPP系ナノコンポジットの調製とiPP母相中でのシリカ分散性 |
| 2.2 | 球晶の結晶構造 |
| 2.3 | 結晶化温度と結晶化度 |
| 2.4 | 結晶化における一次核形成速度と球晶成長速度 |
| 5節 | カーボンナノチューブ/ポリプロピレン複合材料の調整と特性 |
| 1. | CNT樹脂複合材料の調整と特性 |
|
|
| 1.1 | CNT樹脂複合材料の現状 |
| 1.2 | CNT弾性混練法によるCNTの解繊 |
| | −CNT凝集塊の解繊の考え方 |
| | −ポリプロピレン(PP)/EPDM系へのCNTの解繊・分散 |
| | −CNT表面の改質 |
| 1.3 | 二軸押出によるスケールアップ |
| 2. | 樹脂セルレーションと強化機構 |
| 2.1 | 樹脂セルレーションの考え方 |
| 2.2 | 応力緩和による粘弾性モデリング |
| 2.3 | 構造観察と強化モデル |
| 6節 | 木粉との複合化によるポリプロピレンの強度向上 |
| 1. | ウッドプラスチックの歴史 |
| 2. | ウッドプラスチックの特性について |
| 2.1 | WPC の原材料 |
| 2.2 | ウッドプラスチックの製造方法 |
| | −木粉とプラスチックの混練(混合と分散) |
| | −成形方法 |
| 2.3 | ウッドプラスチックの機械的物性(木粉による補強効果) |
| | −曲げ物性,引張物性 |
| | −他フィラー材料との比較 |
| 7節 | ポリプロピレンへのセルロースナノファイバーの分散 |
| 1. | 機械的混合による分散法 |
| 2. | セルロースの疎水化による分散性改善 |
| 3. | 開繊方法による分散性改善 |
| 4. | 高分子分散剤による改質 |
| 8節 | ナノセルロース・リグノフェノール複合体によるポリプロピレンの改質 |
| 1. | 樹木細胞壁 - 利用の歴史と問題点 - |
| 2. | セルロースとリグニン -新しいナノ複合系の設計と誘導- |
| 3. | ナノセルロースーリグノフェノール(LNCC)/ポリプロピレン(PP)複合体の機能 |
| 4. | 光合成を起点とする新しい持続的化学工業システム |
| 9節 | セルロースナノファイバー複合化によるポリプロピレン樹脂の特徴 |
| 1. | セルロースナノファイバー複合化技術 |
| 2. | セルロースナノファイバー複合PP樹脂の特徴 |
| 2.1 | 構造形態 |
| 2.2 | 成形性 |
| 2.3 | 物性 |
| 2.4 | 期待される特性 |
| 10節 | ポリプロピレン,その炭素繊維との複合材料の機械的特性 |
| 1. | 材料と試験方法 |
| 2. | ポリプロピレンの特性 |
| 3. | 短繊維系炭素繊維強化ポリプロピレンの特性 |
|
| |
 |
ポリプロピレンの成形、二次加工技術 |
|
 |
| 1節 | 熱成形におけるポリプロピレン容器の成形 |
| 1. | 成形条件 |
| 1.1 | 予備加熱 |
| 1.2 | 成形 |
| 1.3 | 金型 |
| 2. | ポリプロピレン(PP)成形の特徴 |
| 2.1 | ポリプロピレン(PP)成形の特徴 |
| 2.2 | SPPF 成形 |
| 2.3 | MPPF 成形 |
| 2.4 | 金型温度 |
| 3. | 機能性ポリプロピレン |
| 3.1 | 透明ポリプロピレン |
| 3.2 | PBP |
| 2節 | PPのフィルム・シート・延伸成形 |
| 1.T | ダイフィルム・シート成形 |
| 2. | テンター法二軸延伸成形 |
| 2.1 | テンター二軸延伸工程 |
| 2.2 | 延伸用原反成形 |
| 2.3 | 延伸用樹脂デザイン |
| 2.4 | 二軸延伸評価技術 |
| 3節 | フッ素系加工助剤の機能とその発現機構 |
| 1. | フッ素系加工助剤とは |
| 1.1 | 化学構造と特徴 |
| 1.2 | PPAの特徴 |
| 1.3 | 機能発現メカニズム |
| 2. | 加工助剤の機能 |
| 2.1 | 押出圧力の低減 |
| 2.2 | メルトフラクチャー現象、シャークスキン発生の抑制と成形品の外観や光沢、透明性向上 |
| 2.3 | 目やに発生抑制 |
| 2.4 | 切替時間の短縮 |
| 3. | PPA使用上の注意点 |
| 3.1 | 他の添加剤とのinteraction |
| 3.2 | 食品安全 |
| 4節 | ポリプロピレンの微細発泡技術 |
| 1. | 発泡成形技術とは |
| 2. | 発泡成形の種類 |
| 3. | 発泡成形に用いる発泡剤 |
| 3.1 | 化学発泡剤 |
| 3.2 | 物理発泡剤 |
| 3.3 | 超臨界流体 |
| 4. | ポリプロピレン発泡体の用途 |
| 4.1 | ビーズ発泡ポリプロピレン |
| 4.2 | 架橋発泡ポリプロピレンシート |
| 4.3 | 非架橋発泡ポリプロピレン |
| 4.4 | 発泡ブローポリプロピレン |
| 4.5 | 射出発泡ポリプロピレン |
| 5. | 微細射出発泡成形 |
| 5.1 | 微細発泡成形技術の概要 |
| 5.2 | 微細射出発泡成形のプロセス |
| 5.3 | 微細射出発泡成形の利点 |
| 5.4 | コアバック発泡 |
|
|
| 6. | 発泡用ポリプロピレン |
| 6.1 | 射出発泡用ポリプロピレン |
| 6.2 | 押出発泡用ポリプロピレン |
| 5節 | 樹脂流動制御成形法によるポリプロピレン成形品の評価と配向観察 |
| 1. | 従来の樹脂流動制御成形 |
| 1.1 | 樹脂流動制御の目的とねらい |
| 1.2 | 本方式の概要と特徴 |
| 1.3 | 樹脂流動制御による成形システム |
| | −樹脂流動制御に対応する金型 |
| | −制御システム |
| 2. | 樹脂流動制御成形法による成形品の評価と観察 |
| 2.1 | 成形方法 |
| 2.2 | 成形品の評価 |
| 2.3 | 成形品の観察 |
| | −試験片の製作 |
| | −偏光レーザーラマン分光法による測定 |
| | −偏光レーザーラマン分光法による測定結果と考察 |
| 2.4 | 型内流動可視化システム |
| | −可視化金型の開発 |
| | −石英ガラスインサート設計 |
| | −PEEK 製スペーサー設計 |
| | −撮像系設計 |
| | −ガラス挿入金型を用いた引張試験方法および結果 |
| | −結果と考察 |
| 6節 | ポリプロピレンの精密射出成形および熱ナノインプリントによる微細転写制御 |
| 1. | 射出成形によるマイクロ・ナノ微細構造の転写 |
| 1.1 | 分子構造および分子量分布のマイクロ構造転写性へ影響 |
| 1.2 | 分子構造のナノ構造転写性へ影響 |
| 2. | PPフィルムまたは射出成形品への熱インプリントによるマイクロ・ナノ微細構造の転写性 |
| 3. | 熱インプリント法によるPPナノ繊維作製 |
| 7節 | エレクトロスピニング法によるポリプロピレンのナノファイバー化 |
| 1. | エレクトロスピニング法によるナノファイバー化 |
| 2. | ポリプロピレンのナノファイバー化 |
| 3. | 実験方法 |
| 3.1 | シンジオタクチックポリプロピレン(sPP)溶液の調製 |
| 3.2 | 試験管傾斜法によるゲル化時間の評価 |
| 3.3 | エレクトロスピニング(ES)法によるナノファイバー作製 |
| 3.4 | 有機溶媒およびsPP溶液の物性測定 |
| 4. | ES法によるナノファイバー化のための溶媒選定 |
| 5. | ES法により作製されたsPPナノファイバー |
| 6. | ファイバー形成における有機溶媒の揮発性と電気特性の影響 |
| 7. | ファイバー形成における溶液粘度の影響 |
|
| |
 |
ポリプロピレンの接着性改善,異種材料との接着技術 |
|
 |
| 1節 | ポリプロピレンの表面処理と接着性改善 |
| 1. | ぬれ性と表面張力 |
| 2. | ぬれ性向上と官能基 |
| 3. | コロナ処理 |
| 4. | 低圧プラズマ処理 |
| 5. | 大気圧プラズマ処理 |
| 6. | 火炎処理 |
| 7. | 処理効果の経時変化 |
| 2節 | ポリプロピレン繊維のグラフト重合技術と接着性向上 |
| 1. | 電子線グラフト重合 |
| 1.1 | 電子線照射技術の特徴 |
| 1.2 | 電子線グラフト重合の原理 |
| 2. | 電子線グラフト重合による接着性向上 |
| 2.1 | モノマーの選定 |
| 2.2 | 電子線グラフト重合 |
| 2.3 | 極性の付与と接着性 |
| 3節 | ポリオレフィン樹脂水性分散体の技術と特長 |
| 1. | 塗剤の特長 |
| 1.1 | ソープフリー |
| 1.2 | 保存安定性 |
| 1.3 | 希釈安定性,混合安定性 |
| 2. | 塗膜の特長 |
| 2.1 | 耐水性・耐薬品性 |
| 2.2 | 各種基材との密着性 |
| 2.3 | 接着性 |
| | −アルミニウム箔と PP 樹脂との接着性 |
| | −繊維との接着性 |
| 3. | 用途例 |
| 3.1 | ラミネート用接着剤,アンカーコート剤 |
| 3.2 | 塗料用プライマー,バインダー |
| 3.3 | フィラー等の表面改質剤 |
| 3.4 | インサート成形用接着剤,インモールド成形用接着剤 |
| 3.5 | 保護コート剤 |
| 3.6 | 他のエマルションとの混合,改質 |
| 4節 | ポリシラン添加によるポリプロピレンの融着特性向上 |
| 1. | ポリシラン塗布がPPの熱融着特性に与える影響 |
| 1.1 | 各種試料 |
| 1.2 | 試料調製条件 |
|
|
| | −フィルム調製条件 |
| | −ブレンド試料調製条件 |
| | −融着フィルム調製条件 |
| 1.3 | 各種評価方法 |
| | −T型ピーリングテスト |
| | −FE-TEM 観察 |
| | −DSC測定 |
| | −DMA測定 |
| | −溶融状態における粘弾性測定 |
| 2. | 結果および考察 |
| 2.1 | 融着条件と剥離エネルギーとの相関把握 |
| 2.2 | PP/PMPSブレンド材料のモルフォロジー観察と固体物性に及ぼす影響 |
| 2.3 | PMPS添加PPの溶融状態における分子運動性評価 |
| 5節 | ポリプロピレン用弾性接着剤の特徴,信頼性 |
| 1. | 弾性接着剤の概念 |
| 2. | ポリプロピレン用弾性接着剤の設計 |
| 3. | ポリプロピレン用弾性接着剤の性能および信頼性 |
| 6節 | ポリプロピレン向けホットメルト接着剤の特徴と応用事例 |
| 1. | PPの接着とホットメルトへの要求性能 |
| 1.1 | 従来技術 |
| 1.2 | PP用ホットメルト |
| | −ポリオレフィン系ホットメルトの構成材料 |
| | −ポリオレフィン系ホットメルトの利点 |
| | −ポリオレフィン系ホットメルトの注意点 |
| 1.3 | 反応型ポリオレフィン系ホットメルト(POR) |
| 1.4 | 接着のノウハウ、注意点 |
| 2. | PP用ホットメルトの用途例 |
| 2.1 | OPPフィルムの貼り合せ(例:プラスチック封筒の組立) |
| 2.2 | PPと異種材料の貼り合せ(例:自動車内装材の組立) |
| 7節 | PPフィルムのヒートシール技術とシール特性の向上 |
| 1. | ヒートシールとは |
| 2. | 高分子ヒートシールの基本 |
| 3. | ヒートシールするフィルム材料 |
| 3.1 | PE |
| 3.2 | PP |
|
| |
 |
ポリプロピレンの応用事例 |
|
 |
| 1節 | ポリプロピレン製中空構造板の特徴と自動車部材への応用 |
| 1. | ポリプロピレン製中空構造板の構造及びその製造方法 |
| 1.1 | 並行リブタイプ |
| 1.2 | エンボスシートサンドイッチタイプ |
| 1.3 | ハニカムシートサンドイッチタイプ |
| 1.4 | その他 |
| 2. | ポリプロピレン製中空構造板の特徴 |
| 2.1 | 一般物性 |
| | −ポリプロピレン製中空構造板を特徴付ける一般物性 |
| | −代表的な一般物性値 |
| 2.2 | 吸音特性 |
| | −ヘルムホルツ共鳴 |
| | −代表的な吸音特性 |
| 2.3 | その他の特徴 |
| | −カット,打ち抜き加工 |
| | −各種熱加工 |
| | −他部材との貼合せ複合化 |
| 3. | 自動車部材への応用 |
| 3.1 | トランクボード |
| 3.2 | シートバックパネル |
| 3.3 | バックドアパネル,サイドドアパネル |
| 3.4 | バッテリーカバー |
| 3.5 | その他の応用例 |
| 2節 | ノンフィラーポリプロピレンの発泡成形技術と自動車部材への応用 |
| 1. | 自動車内装トリムの軽量化 |
| 1.1 | 戦略 |
| 1.2 | 射出成形品の軽量化 |
| 2. | 発泡成形技術 |
| 2.1 | スワルマークの発生メカニズムと抑制 |
| 2.2 | ゆず肌の発生メカニズムと抑制 |
| 3. | 発泡成形品の性能 |
| 3節 | PPシート,容器の高透明化とその応用展開 |
| 1. | 溶融樹脂膜の外部ヘーズに及ぼす押出スクリュー形状の影響および内部ヘーズに及ぼすダイス内剪断応力の影響 |
| 1.1 | 基本形状による予備評価 |
| 1.2 | スクリュー形状の最適化 |
|
|
| 1.3 | 透明性に与えるダイ内剪断応力の影響 |
| 2. | 高透明性PPシート製造に寄与する因子の解析 |
| 2.1 | 透明性に与える立体規則性の影響 |
| 2.2 | 透明性に与える分子量分布の影響 |
| 2.3 | 透明性に与える透明改質剤としてのL-LDPE添加の影響 |
| 3. | 高透明シートの用途展開 |
| 4節 | ポリプロピレン系シュリンクフィルムのガスバリアシュリンクフィルムへの応用 |
| 1. | チューブラー2軸延伸装置 |
| 2. | 各種シュリンクフィルムの水蒸気バリア性,酸素バリア性 |
| 3. | ガスバリアシュリンクフィルムの物性 |
| 5節 | ポリプロピレンのアウトドアウエア素材への応用事例 |
| 1. | ポリプロピレンがアウトドアウエアに使われてきた歴史 |
| 2. | ポリプロピレンの特性 |
| 2.1 | 疎水性 |
| 2.2 | 軽量 |
| 2.3 | 熱伝導性 |
| 3. | ポリプロピレンの問題点 |
| 3.1 | 非染色性 |
| 3.2 | ピリング |
| 3.3 | 耐熱性 |
| 3.4 | 疎水性 |
| 4. | アウトドアウエアへの応用事例 |
| 4.1 | 吸湿発熱素材を使用したアンダーウエア |
| | −発想のきっかけ |
| | −濡れ戻り防止 |
| | −軽量,保温性,風合いソフト |
| | −問題点 |
| 4.2 | 肌面ドライなアンダーウエア |
| | −発想のきっかけ |
| | −疎水と吸水のバランス |
| | −問題点 |
| 4.3 | 大量発汗対応ボーダーインナーシャツ |
| | −発想のきっかけ |
| | −非染色性と疎水性 |
| | −問題点 |
|
| |